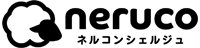ベッドにはさまざまなサイズがあり、暮らし方や設置するスペース、使用人数に合わせてサイズを選ぶ必要があります。
家族と一緒に眠りたい、1人でもゆったりとしたスペースを確保したいと考えている方は「セミダブルベッド」がおすすめです。シングルベッドより幅が20cm広いセミダブルベッドなら、それほど圧迫感を感じずに使用できるでしょう。
また、ベッドを選ぶ際は機能性も重視する必要があります。なかでも、カビやダニの発生を抑えたいなら「すのこベッド」が最適です。すのこベッドはデザインの種類も豊富で、セミダブルサイズのものも見つかるでしょう。
今回は、セミダブルのすのこベッドに注目し、選び方やメリット・デメリットを解説します。おすすめのベッド10選も紹介しますので、気になるものがあればぜひチェックしてみてください。
目次 [開く]
希望通りのベッドが見つかる!おすすめセミダブルすのこベッド10選

デザインや機能、素材などすのこベッドを選ぶポイントはたくさんあります。また、設置するお部屋にあるインテリアや使用している寝具とのコーディネートのしやすさなども考えておくと、ベッドだけが浮いてしまうこともありません。
希望の条件にぴったり当てはまるベッドが見つかるのが一番ですが、条件に優先順位を付けておくとあれもこれもと迷うことなく、本当に自分が必要だと思うことを見つけやすくなります。
絶対に妥協できない条件と妥協しても構わない条件を分けておき、最初に当てはまらないものを除外していくと迷ってしまって決められず、結局どれが良いのかわからなくなったということもなくなるはずです。
ここでは、素材やデザイン、機能に特徴のあるおすすめのセミダブルすのこベッドを厳選してご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
頑丈設計セミダブルすのこベッド
レイアウトが自由に選べるヘッドレスデザイン。高さは4段階に調節可能で、耐荷重も350キロあるので子供部屋にも夫婦の寝室にもおすすめです。
総檜のセミダブルすのこベッド
国産檜を贅沢に使用した天然木のすのこベッドはマットレスでも布団でも使用可能。床面の高さは3段階に調節できるので、床面下を収納としても活用できます。
便利な棚付きセミダブルすのこベッド
2口コンセントと棚が付いた便利なセミダブルベッド。並べて設置しやすいフラットなフォルムと開放的なデザインで、お部屋を広く見せてくれます。
島根県産天然木檜セミダブルすのこベッド
国産の檜を無塗装で使用しているので、天然木ならではの温もりや質感を感じられるベッド。檜の調湿作用で一年を通して快適におやすみいただけます。
スリムな奥行きの宮棚付きセミダブルすのこベッド
天井との間にたっぷりと距離を取れるロータイプ。飾り棚としても使えるヘッドボードにはスマートフォンなどの充電に便利なコンセント付きで、ベッド回りを自分好みに飾れます。
温もりあふれる北欧調デザインのセミダブルすのこベッド
天然木を使用した北欧調デザインのすのこベッド。床面の高さは3段階に調節可能、ヘッドボードはコンセント付きで、棚にはタブレットやスマートフォンを立てかけることもできます。
当社オリジナルのヴィンテージ調ベッド「アーヴィング」
味わい深い表情の木目と武骨なアイアン脚が合わさった、ヴィンテージ調の木製ベッドです。ヘッドが付いていないため、ヘッド付きベッドよりも省スペースで自由なルームメイキングが可能です。
スマート&シンプルなデザインベッド「REGLS2(レグルス2)」
スリムなスチール脚の無駄が一切ないシンプルなデザインです。お部屋のスペース、イメージを問わずご使用いただけます。オールスチール製なのでカビが発生する心配なし!さらに木製のベッドに比べ頑丈です。
ベッド下は収納ケースなどを置くスペースとしても大活躍します。
組立簡単で気軽にDIY気分が楽しめる!E-DIYパレットベッド
当社オリジナルの、大型の木製パレットベッドが作れるDIYキットです。ネジ穴に合わせてドライバーでネジを締めるだけで簡単にシングルサイズの木製パレットベッドフレームが作れます!
引き出し付きセミダブルすのこベッド
洋服や寝具を収納できる引き出し付きのすのこベッド。置いたものの落下を防いでくれる前板付きの棚には、スマートフォンの充電に便利なコンセントとUSBポートが付いています。
セミダブルのすのこベッド選びの7つのポイント

セミダブルのすのこベッドはデザインや素材にたくさんの種類があるので自分の好みに合ったものを選びやすい反面、種類が多すぎてどれを選べばわからなくなる人も多いようです。
ベッドは寝室の印象を左右するインテリアでもあり、選び方に失敗したからといって簡単に買い替えることもできない高額なインテリアでもあります。
どのような印象のお部屋にしたいのか、どのような機能が必要なのかなどさまざまな条件で比較して、納得できるベッドを選ぶためのコツを7つご紹介します。
1.設置場所に合うデザインで選ぶ
床板がすのこ状という共通点はあるものの、すのこベッドのデザインはさまざまで素材によっても大きく印象が変わります。
寝室をリラックスできる空間にしたいときには、木の温もりが感じられる色使い、素材を選ぶのがおすすめですし、高級感のあるシックな寝室が好みなら重厚なカラーやデザインのベッドがおすすめです。
国産の檜や桐が使われたものは香りの良さが特徴、パイン材は素朴な雰囲気でカントリー調のインテリアや北欧デザインの家具との相性が良く、価格も手頃なものが多いようです。
また、ベッドフレームにレザーやファブリックが使われたものは、ヘッドボードにもたれてソファ代わりにくつろぐこともできます。どのようなイメージにしたいのか、しっかりと思い描いてからベッドを選ぶと理想通りの寝室が作れるはずです。
2.素材で選ぶ

たくさん種類があるすのこベッドの素材ですが、よく使われているのは杉、桐(きり)、檜(ひのき)、パイン材などの木材です。木の風合いや香りを楽しみたいのであれば、木製のベッドを選びましょう。
木材は種類によって特徴が異なります。それぞれ以下のような特徴やメリット・デメリットがありますので、素材選びの参考にしてください。
| 素材 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 杉 | ・軽量でやわらかい ・比較的安価 |
・軽量 ・香りが良く防虫効果がある ・調湿効果が高い ・有害物質の吸着効果に優れる |
・傷つきやすく耐久性が低め ・湿気を吸いやすい z |
| 桐(きり) | ・非常に軽量でやわらかい ・湿気に強い |
・軽量 ・防湿効果が高い ・耐火性が高い ・防虫・防カビ効果 |
・傷つきやすく強度が低め ・高価 |
| 檜(ひのき) | ・高級木材 ・耐久性がある |
・耐久性が高い ・防虫効果 ・腐りにくい ・香りが良くリラックス効果がある |
・高価 ・重い |
| パイン | ・針葉樹でやわらかい ・比較的安価 |
・加工がしやすくデザインが多様 ・明るい色合いのため部屋に馴染みやすい |
・やわらかく傷つきやすい ・湿気に弱い |
また、木材ではなくスチールや樹脂が使われる場合もあります。
| 素材 | 特徴 |
|---|---|
| スチール | カビの心配がなく耐久性にも優れており、比較的安価なものが多い |
| 樹脂 | 軽量で耐久性が高く、カビの心配がなくお手入れが簡単 |
木製のすのこベッドは通気性が高く、カビが発生しにくいとはいえお手入れ次第でカビが生える心配があります。しかし、樹脂やスチールの場合は素材そのものにカビが生える心配がないため、衛生面を第一に考えるのであれば、スチールや樹脂がおすすめです。
ただ、スチール製や樹脂製のすのこベッドは、選べるデザインが少ないというデメリットもあります。セミダブルサイズなど少し大きなサイズになると選択肢がさらに少なくなることもあるため、素材、デザイン、サイズのどれを優先するのかを事前に決めてから選ぶようにしましょう。
3.耐久性や耐荷重で選ぶ

ベッドを安全に使用するためには、どのくらいの重さに耐えられるのかを示す耐荷重のチェックが必須です。
すのこベッドは床板の間に隙間がありますが、板の厚みを増し、間隔を狭めることで耐荷重を上げているものも増えてきているため、強度が高く安心して使えます。
床板に使われたすのこがしっかりしていると寝返りをうったとき、起き上がるときなどに軋む心配もありません。
1人で寝る場合は100キロ程度の耐荷重でも十分ですが、2人で寝るときは耐荷重が高いものを選んでおくと不安なく眠れます。
また、重いマットレスを使用する場合は、マットレスの重さがプラスされることも考えたうえでベッドを選ばなければなりません。マットレスと寝具の重さを足しても余裕がある耐荷重のベッドを選んでおけば、厳選したお気に入りのベッドを長く使い続けることができます。
4.ベッドフレームの機能で選ぶ

ベッドフレームにどのような機能を求めるのかによっても、おすすめのベッドは変わってきます。
できる限りシンプルに、圧迫感なく設置できるものが希望であればヘッドボード、フットボードなどがないヘッドレスベッド、ちょっとした小物を置くナイトテーブルを設置する余裕もない手狭な寝室なら棚代わりになるヘッドボード付きのベッドフレームもよいでしょう。
ヘッドボードがあると圧迫感を感じるかもしれませんが、収納スペースを確保できると考えれば検討の余地はあります。
できる限り薄く、高さを抑えてあるヘッドボードならベッドの周りがすっきり片付き、さらにベッド自体もコンパクトに収まるのでスペースの限られたお部屋にもおすすめです。
都市部のマンションでは子ども部屋や夫婦の寝室に使える部屋のサイズもそれほど大きくないため、機能性の高いベッドを設置することで使い勝手が良くなることもあります。
スマートフォンなどの充電に便利なコンセント、ナイトスタンド代わりになる照明、雑誌や眼鏡、目覚まし時計を置ける棚など、ベッドの機能にはさまざまなものがあります。ベッドにどのような機能が付いていると便利なのかを考え、必要な機能がそろっているかをチェックしてから購入しましょう。
ベッドのおもな機能とメリット・向いている人
| 機能・種類 | 特徴 | メリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 収納付き | 引き出しタイプ、跳ね上げタイプ、チェストタイプがある | ・本や小物を収納でき、スペースの有効活用ができる ・跳ね上げタイプはベッド下がすべて収納スペースなのでラグなどの長物や羽毛布団なども収納可能 |
・収納が少ない人 ・収納スペースを増やしたい人 |
| コンセント付き | コンセントのほか、USBポート付きもある | ・スマートフォンや電子機器を充電できる | ・ベッドでスマートフォンやタブレットを充電したい人 |
| 照明付き | ヘッドボードに照明が内蔵されている | ・読書や作業に便利 ・部屋の雰囲気作りにも役立つ |
・読書や作業をする人 ・ベッド周りをおしゃれにしたい人 ・夜中にトイレに行くことが多い人 |
| 高さ調節機能付き | ベッドの床面高さを調節できる | ・自分の好みに合わせていつでも調節可能 ・ローベッドや、ベッド下収納が作れる。また、ハイベッドにもなる |
・模様替えや、ライフスタイルに合わせてベッドスタイルを変えたい人 |
| サイドテーブル付き | サイドテーブルが一体化されている | ・飲み物や眼鏡、時計などの小物を置くスペースが確保できる | ・ベッド周りに必要なものを置きたい人 |
| 折り畳み式 | コンパクトに折り畳み可能、ロール式もある | ・使用しないときにコンパクトに収納可能 ・スペースを節約可能 ・移動に便利なキャスター付きのものもある |
・部屋のスペースを有効活用したい人 ・部屋が狭い人 ・来客用ベッドがほしい人 |
| ヘッドレスタイプ | ヘッドボードがない | ・シンプルでミニマルなデザイン ・部屋のスペースを広く使える ・棚がないのでホコリが気にならない |
・部屋を広く使いたい人 ・シンプルなデザインが好きな人 |
| パネルタイプ | 棚がないフラットなパネル型ベッド | ・シンプルでミニマルなデザイン ・背もたれとして使える ・圧迫感がない |
・部屋を広く使いたい人 ・シンプルなデザインが好きな人 |
5.高さで選ぶ
ベッドの高さは床面とほぼ同じ低めのタイプから、高さ200cmに近いハイタイプまでさまざまです。高さは使い心地や部屋の雰囲気に影響を与えます。以下の表のメリット・デメリットをふまえたうえで、自分に合った高さのものを選びましょう。
| 高さ | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 低め | ・床面とほぼ同じ〜10cm程度の高さ ・「ローベッド」や「ステージベッド」などと呼ばれる |
・天井を広く感じ、開放感がある ・落下時の危険性が少ない |
・ベッド下のスペースを収納として活用できない |
| 中程度 | ・一般的な高さで、床面までの高さが30〜40cm程度のものが多い | ・購入の選択肢が幅広い ・腰かけるのに便利 |
・ベッド下のスペースを収納として使えるが、高さが物足りないと感じるかもしれない |
| 高め | ・床面下に収納スペースが付いたものが多い ・床面が50cm以上になることが多い |
・機能性に優れる ・ベッド下を有効活用できる ・立ち上がりが楽 |
・価格が高い ・重心が高く、サイズが大きい |
| ハイタイプ | ・高さが200cm近いものもあり、ロフトベッドやシステムベッドに分類される | ・ベッド下を大きく活用できる ・ベッド下にもマットレスや布団を敷くと2段ベッドのように使える |
・天井が近く、大人は圧迫感を感じることがある ・移動や組み立てで労力が必要 |
6.お手入れのしやすさで選ぶ

ベッドメイクは毎日するものなので、お手入れが楽なものを選びましょう。
布団を載せて使うすのこベッドの場合は、ベッド自体が布団干しの台になるもの、キャスター付きで移動が簡単にできるものが便利です。
天気が悪い日もすのこベッドを立てて布団をかけておけば湿気対策も万全、手狭なお部屋で昼間はベッドを畳んでしまいたいときにも折り畳みタイプがよいでしょう。
バネで簡単に折り畳めるベッドならお年寄りや女性でも安心できます。指を挟まないように設計されているもの、ストッパー付きのキャスターなど安全面への配慮についても確認しておきましょう。
7.価格で選ぶ
価格帯でもベッドの特徴は異なります。高ければ高いほど良い、というわけではないため、価格別のメリット・デメリットを理解して最適な価格を選びましょう。
| 価格帯 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 安いベッド (~2万円以下) |
・価格が手頃なものが多い ・組み立てが比較的簡単 ・軽量で移動が楽 |
・耐久性が低い(短期間の使用に向いている) ・素材が安価なため、見た目が劣る ・機能が少ない ・保証期間が短い、またはない |
| 高いベッド (2万円以上) |
・高品質な素材で耐久性が高い(天然木、国産など) ・洗練されたデザイン ・機能が豊富(収納、コンセント、照明、高さ調節など) ・保証期間が長い |
・価格が高い ・重量があり、移動や組み立てが大変 |
セミダブルベッドの特徴とメリット・デメリット

セミダブルベッドの特徴とメリット・デメリットを解説します。
セミダブルベッドの特徴
セミダブルのベッドは、名前に「ダブル」と付いているものの、2人で寝ることを前提としているのではなく、シングルサイズでは窮屈に感じる人が広々と寝るために適したサイズと考えるのがベストです。
シングルベッドの幅は90cm~100cm、ダブルベッドは140cm、セミダブルベッドの場合は120cmなので、シングルとダブルのちょうど中間、1人だと広く、2人だと少し狭いサイズ感といえるでしょう。
ベッドの幅は「左右20cmずつ寝返りをうつ余裕」+「肩幅」で考えると良いとされています。女性の平均的な肩幅は約40cm、男性は45cmなので、それぞれ80cm、85cmがベッドの幅として必要ということです。
あくまでも平均的なサイズ、最低限必要とされるサイズなので、余裕を持って寝たいときにはゆとりのあるベッド幅を選ばなければなりません。
セミダブルベッド使用のイメージ
| 使用人数 | 使用イメージ |
|---|---|
| 大人1人 | 大柄な男性でもゆったりと眠れます。ロータイプのものを選べば圧迫感を抑えられるでしょう。 |
| 大人2人 | 横にはなれますが寝返りをうつのは難しいでしょう。来客時など、一時的に使用するのなら問題ありません。 |
| 大人1人+子1人 | 余裕はそれほどありませんが寝返りがうてないほど窮屈さは感じないでしょう。子どもの体格が大きくなってくると、手狭に感じるかもしれません。子どもと使用するなら、子どもがベッドから落ち内容、設置場所などを工夫しましょう。 |
先述のとおり、セミダブルベッドは1人で広く使うことを想定して作られているものがほとんどです。そのため、耐荷重も1人分になっていることが多く、一般的に100キロ~120キロに設定されています。
大人2人で寝ることを想定しているのであれば、できるだけ耐荷重の大きなものを選んでおきましょう。もちろん、耐荷重を超えたからすぐに壊れるというものではなく、安全に使用するためにメーカーが保証している数値ではありますが、耐荷重を超えて使用した場合は安全に長く使うことはできません。
耐久性、安全性を確保するためにも、耐荷重はしっかり確認しておいてください。
セミダブルベッドのメリット
セミダブルベッド最大のメリットは広さです。シングルでは窮屈さを感じていた体格の大きな人や寝相の悪い人でも、セミダブルベッドなら快適に眠れるでしょう。広々と寝たいけれどダブルベッドを買うほどではない、という方の選択肢としてもセミダブルベッドは最適です。
セミダブルベッドとシングルベッドとの幅の違いは20cmほどあり、想像以上にベッドを広く感じるかもしれません。部屋に余裕があるならぜひセミダブルベッドを検討してみてください。
セミダブルベッドのデメリット
ベッドは大型家具の一つで、設置するだけで部屋を圧迫してしまいます。セミダブルベッドを設置するとシングルベッドを置くよりさらに圧迫感を感じやすくなるでしょう。ベッドがほかの家具や部屋の入口ドアに干渉してしまう場合もあるため、設置する前にスペースを確保できるかしっかりと確認しておくことが大切です。
設置場所と併せて搬入できるかどうかも確認しておきましょう。組み立てが必要な場合は、組み立てスペースを確保できるかもチェックが必要です。
また、1台あたりの使用人数によって使用する寝具のサイズも異なるため、シングルベッドの寝具よりもコストが高くなる可能性があります。
すのこベッドの特徴とメリット・デメリット

すのこベッドの特徴とメリット・デメリットを解説します。
すのこベッドの特徴
通常、ベッドの床板は1枚の板になっていますが、すのこベッドの場合は床板がすのこのような形状になっています。板と板の間に空気の通り道ができ、ベッド下に湿気がこもりにくい構造なので通気性が良くお手入れも簡単です。
すのこベッドには基本的にマットレスを載せて使用します。なかには布団でもマットレスでも使えるすのこベッドもあるため、どのような寝具を使いたいかを考えて種類を選ぶとよいでしょう。
すのこベッドのメリット
すのこベッドと一口にいってもベッドフレームにすのこ状の床板が付いたものもあれば、すのこそのものに脚が付いたようなもの、ロール状になったもの、折り畳みが可能なものなど、デザインはさまざまです。
折り畳み可能なすのこベッドのなかには、布団を干せるものなどもあります。ライフスタイルやお部屋の間取りに合わせて、好みのものを見つけやすいでしょう。
また、すのこベッドは通気性が良く、布団やマットレスの汗や湿気を逃がしてくれるので、ニオイや雑菌の繁殖を抑える効果が見込めます。素材に木材を使用しているものを選べば、木のリラックス効果も期待できるでしょう。
女性でも簡単に扱える軽量なタイプが多く、すのこベッドの特徴で毎日の掃除やベッドメイク、模様替えなども軽いすのこならラクラクです。
すのこベッドのデメリット
すのこベッドは通気性が高いため、冬になると寒さを感じやすくなります。冬はしっかりと防寒対策しておきましょう。また、すのこベッドの底面は通気性をスムーズにするため、ベッド下にものを置くと、通気性が悪くなりカビが発生する原因になってしまいます。そのため、ベッド下にはなるべくものを置かないようにしましょう。
また、すのこベッドは硬さを感じやすいため、薄手の布団・マットレスの使用には向きません。厚手の布団・マットレスを使用しましょう。
木製のすのこベッドの場合、軋み音が気になる可能性があります。軋み音の原因がわかれば音を軽減できる場合もあるため、原因を特定して対処しましょう。軋み音への対処法は下記関連記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
すのこベッドに合う【20,000円以下】おすすめマットレス3選

すのこベッドには布団を敷いて使えるものもありますが、寝心地を重視するのであれば好みの硬さのマットレスを使うのがおすすめです。
マットレスは種類や厚みによって寝心地が変わりますが、高価なものが良いというわけではなく、手頃な価格でも快適に眠れるものがたくさんあります。
ここでは、20,000円以下で購入できる安くて寝心地の良いおすすめマットレスを3種類ご紹介します。
高密度ポケットコイルセミダブルマットレス
ベッド・コンシェルジュ nerucoオリジナルのポケットコイルスプリングマットレス。日本人の体格を考慮して作られ多マットレスが、心地良い眠りをサポートします。
ネルコオリジナル ポケットコイルセミダブルマットレス
高密度のポケットコイルが体圧を分散、独立したスプリングが寝る人の体重や体型に合わせて変化し、身体をしっかりと支えてくれます。
三つ折りポケットコイルセミダブルマットレス
ファスナーで3分割も可能な三つ折りタイプのポケットコイルマットレス。日本人の体格に合わせて作られているので、硬すぎず、やわらかすぎずの快適な寝心地を体感できます。
【よくある質問】すのこベッドの疑問を解決!

すのこベッドを購入しようとは思っているけれど、購入前に知っておきたいこと、ほかのベッドと何が違うのかなど、疑問がある方も多いのではないでしょうか。ここでは、Q&A方式ですのこベッドの疑問についてお答えしていきます。
Q.1 すのこベッドはカビ対策になりますか?

A.1
通気性に優れたすのこベッドは、カビ対策としてもお使いいただけます。
ただし、すのこだから絶対にカビが生えないというわけではないため、使用方法に気を付けることは大事で、定期的なお手入れも必要になります。
また、使われている素材によってカビが生えやすいものもあるため、お手入れの頻度が下がってしまいそうなときには、カビの生えにくい素材選びも大事です。
湿気に強い素材としておすすめなのは桐と檜ですが、耐久性を優先するのであれば檜、扱いやすさを優先するのであれば軽さが特徴の桐を選びましょう。
木製すのこにこだわらないのであれば、軽量で扱いやすい樹脂製のすのこベッドも選択肢に入れてみてください。どのような素材を選ぶにしても「布団やマットレスはマメに干す」、「寝室の換気を行なう」、「除湿マットを敷く」というのがカビ対策の基本になります。もし、カビが生えてしまった場合は、カビが生えたところをアルコールで拭きとり、しっかり乾燥させましょう。
布団やマットレスにもカビが生えてしまっていることがあるため、すのこベッドだけでなく寝具もカビの除去を行なってください。基本のカビ対策として除湿マットの使用は重要ですが、布団やマットレスを敷きっぱなしにしないという場合は、必ずしも必要というわけではありません。
ただし、汗かきの人で目が覚めると寝具が湿っているという場合、快適に眠るために除湿マットを使用するのもよいでしょう。
Q.2 すのこベッドの形状による違い、通常のベッドとの違いは何?

A.2
まず、すのこベッドと通常のベッドは床板の形状が異なります。通常のベッドは床板が2枚か2枚の大きな板のため通気性が期待できず、マットレスにカビが生えたり、湿気によって傷んでしまったりしやすいといわれています。
ただし、大きな板でマットレスを支えるため耐荷重が大きく、耐久性にも優れているのが通常のベッドの特徴です。
一方、すのこベッドの場合は床板がすのこ状のため通気性には優れているものの、どうしても耐荷重が低く、耐久性が劣ることも少なくありません。
しかし、すのこの厚み、板の間隔を工夫することで通常のベッドと変わらない耐久性を持つすのこベッドも増えています。
すのこベッドの形状はロール式、三つ折りや二つ折りなどの折り畳み式、すのこに脚が付いたタイプなどさまざまですが、収納しやすいのはロール式や折り畳み式です。
脚が付いたタイプはベッド下に衣装ケースなどを入れて使うこともできるため、収納家具を置くスペースがない寝室にもおすすめです。
また、布団を敷いて使う場合には折り畳んだすのこを布団干しに使えるベッドもあるため、使用する寝室の広さ、寝具、ライフスタイルに応じて選びましょう。
Q.3 すのこベッドに合わせるのは布団?マットレス?

A.3
すのこベッドには、敷布団が使えるものとマットレス専用のものがあるので、どちらを使うのか決めてからベッドを選ぶ、あるいは将来的に変更することを見越して、どちらも使えるものを選んでおくようにしましょう。
布団が使えるタイプのすのこベッドは折り畳めるものも多く、布団の上げ下ろしは面倒だけれど、ベッドを置くと部屋が狭くなるのが困るという場合に向いています。
ただし、敷布団の厚みが十分でないと寝心地が悪くなることもあるので、高反発マットレスや厚みのある敷布団と折り畳めるすのこベッドの組み合わせがよいでしょう。
Q.4 すのこベッドは寝ているときに軋みやすい?

A.4
すのこベッドに限らず、ベッドの軋みを完全になくすことは不可能といわれています。その理由は、多くの部材を組み合わせて作られているという構造上、どうしても軋み音がしてしまうからです。
ベッドの軋み音は、フレーム、床板、ベッドとフローリングの床の接地面から発生するといわれています。
フレームの軋みを軽減するには、ヘッドボードやフットボードがない、できるだけシンプルなものを選ぶのが良く、床板の軋みを軽減するにはしっかりとした厚みのある床板、強度の高い床板が使われているものを選ぶことがポイントです。
すのこベッドの場合、どうしても床板がしなりやすいため厚み、すのこ板の間隔を確認し、丈夫なものを選ぶことで軋みが軽減されます。
フローリングの接地面から発生する軋みには軽いベッドを選ぶ、ベッドの下にカーペットを敷くなどの対策が有効です。
マットレスを使用している場合、マットレスから軋み音が発生していることもあります。ベッドの軋み対策をしても音が気になるときは、マットレスが軋んでいないかも確認しておきましょう。
Q.5 2台並べて使うのに適したすのこベッドは?
A.5
キングサイズのベッドやクイーンサイズのベッドは広々としていて、ゆったり手足を伸ばして眠れますが、搬入やお手入れが大変、合わせる寝具の選択肢が少なくなるなどのデメリットも少なくありません。
しかし、ベッドを2台並べることで大きなベッドと同じスペースを確保することができます。
すのこベッドを2台並べることを考えているのであれば、段差や隙間ができないものを選びましょう。
お子様とご夫婦で寝られるのであれば、お子様が小さい間はロータイプで安心して眠れるように、大きくなったら少し高くしてベッド下を収納スペースにと床面の高さを調整できるものも便利です。
寝ている間にずれることがないよう、しっかり連結できる金具付きなど、もともと並べて使うことを想定して作られたすのこベッドもたくさんあります。
家族が増えてもベッドを買い替えることなく、連結して使ったり、別々に使ったりとフレキシブルな対応が可能なすのこベッドもたくさんあるので、ライフステージに合わせて選びましょう。
Q.6 冬はすのこベッドが寒く感じる?

A.6
すのこベッドは通気性が高く、空気の通り道を作ることができるという特性を持っていますが、冬は通気性の高さのせいで寒く感じることもあるようです。
脚付きすのこベッドで床面下を収納として使用している場合、冷気をシャットアウトすることもできますが、床面下に何もない場合は冷たい空気が布団やマットレスを通過して、体を冷やしてしまいます。
特に床面との距離が近いロータイプのすのこベッドは、床の冷たさが伝わりやすいので快適に眠るためにも寒さ対策が必要です。
床にコルクマットや厚手のラグを敷く、マットレスや布団の下に断熱シート、アルミシートを敷く、保温性の高いベッドパットを使用するといった工夫で暖かく眠ることができるでしょう。
ただし、断熱シートやアルミシートは通気性がないので湿気がたまるとカビやニオイの原因になります。普段よりもお手入れをマメにし、寒い時期が終わったら忘れずに取り除くようにしてください。
また、寝室自体を温かく保つためには窓に断熱シートを張ったり、床まで届くカーテンを使用したりするのもおすすめです。
寝室のスペース、家具との配置の都合でベッドを窓際に置いている場合は、特に窓からの冷気に影響を受けやすいのでカーテンを2重にしたり、厚手のものに変えたりといった対策も必要かもしれません。
セミダブルのすのこベッドは種類が豊富な「ネルコンシェルジュ」がおすすめ
セミダブルサイズのベッドはゆったりとした一人寝はもちろん、お子様との添い寝用、シングルサイズのベッドと並べて、ご夫婦と小さなお子様といった家族構成でもお使いいただけます。
また、すのこベッドは通気性が良く、1年を通して湿気やカビの発生を抑えられます。種類も豊富で、希望の条件にぴったりのものを見つけることができれば、長く愛用できるでしょう。
簡単に買い替えられるものではないベッドだからこそ、本当に納得できるものを選びたいと思うのは当然です。素材やデザイン、機能、耐久性、高さ、手入れのしやすさ、価格などを比較しながらぜひお気に入りのベッドを見つけてみてください。
ベッド・マットレス通販専門店のネルコンシェルジュでは、今回紹介したベッド以外にも、多数のすのこベッドを取り扱っています。すのこベッドをお探しの場合は、ぜひ下記リンク先をチェックしてみてください。